・大企業で感じるモヤモヤや不安
・そのモヤモヤや不安の解決策
大企業で働いている方の中には、大企業病にうんざりしている方が多いと思います。また、新入社員や若手の方も色々な場面でモヤモヤを感じている人が多いと思います。
私も10年以上大企業で勤務していたため、その気持ちは非常に良くわかります。
この記事では、若手が大企業病に対して感じるモヤモヤや不安の概要と、その解決策について丁寧に解説していきます。
大企業病にうんざりしたからといって、いきなり「転職しよう」と考えるのではなく、まずは「VIEW」や「ミイダス」を使って自分の市場価値や強み弱みを知り、冷静にキャリアの選択肢を考えるのがオススメですよ。
- まとめ|大企業病へのうんざり事例20選とその解決策
- 1.大企業若手のモヤモヤ・不安
- 1)新入社員研修が長い
- 2)現場実習に送り込まれる
- 3)配属ガチャ・上司ガチャでハズレを引く
- 4)飲み会幹事を若手がやらされる
- 5)ぶら下がりの働かないおじさんが多い
- 6)報連相ができず上司から怒られる
- 7)仕事がぬるい・楽すぎる・ぬるま湯
- 8)成長できない・スキルが身につかない
- 9)業務が調整ばかりでつまらない
- 10)組織が縦割りで交流がない
- 11)ルールがガチガチ
- 12)社内向けの無駄な仕事が多い
- 13)提案やチャレンジをしにくい
- 14)稟議や決裁に1週間以上かかる
- 15)社内資料の体裁に非常にこだわる
- 16)周りが優秀でついていけない
- 17)副業が禁止されている(という勘違い)
- 18)優秀な人が辞める
- 19)若手の退職が多い
- 20)うつ病で休職する人が多い
- 2.モヤモヤ・不安の解決策
- 3.まとめ
- 4.関連記事
まとめ|大企業病へのうんざり事例20選とその解決策
まずはまとめから。大企業の若手社員がよく感じるモヤモヤ・不安は以下の通りです。
1)新入社員研修が長い
2)工場実習に送り込まれる
3)配属ガチャ・上司ガチャでハズレ
4)飲み会幹事を若手がやらされる
5)働かないおじさんが多い
6)報連相ができず上司から怒られる
7)仕事がぬるい・楽すぎる・ぬるま湯
8)成長できない・スキルがつかない
9)業務が調整ばかりでつまらない
10)組織が縦割りで交流がない
11)ルールがガチガチ
12)社内向けの無駄な仕事が多い
13)提案やチャレンジをしにくい
14)稟議や決裁に1週間以上かかる
15)社内資料の体裁にこだわる
16)周りが優秀でついていけない
17)副業が禁止(という勘違い)
18)優秀な人が辞める
19)若手の退職が多い
20)うつ病で休職する人が多い
続いて、そんなモヤモヤ・不安を感じた時の解決策は以下の通りです。
1)自分の市場価値や強み弱みを知る
2)自己投資・スキルアップをする
3)上司に異動を願い出る
4)専門家にキャリア相談する
5)転職活動を始めてみる
前述の通り、大企業病にうんざりしても、いきなり転職を考えるのではなく、「VIEW」や「ミイダス」で自分の市場価値や強み弱みを知り、冷静にキャリアの選択肢を考えましょう。
1.大企業若手のモヤモヤ・不安
1)新入社員研修が長い
1つ目は「新入社員研修が長い」です。
様々な制度や仕組みが整っている大企業では、入社後の新入社員研修でそれらについてみっちりと研修が行われます。
また、知識教育以外にも、マナー研修やコミュニケーション研修、集団行動など様々なプログラムが準備されており、多くの企業では配属までに1〜3ヶ月程度の研修が行われます。
入社後の数ヶ月は実務に関われないことには良し悪しありますが、中小規模の会社では数日の研修の会社も多くあるため、大企業ならではのポイントだと言えます。
Twitterでも、新入社員研修が長いことには賛否両方の意見がありました。
ポジティブな意見
おはようございます🌞
— なぎさ|エンキャリを目指す22卒 (@nagisaoka22) August 31, 2022
今日が新卒研修最終日。
5ヶ月なんて長いと思っていたけど
濃い時間すぎて一瞬だった。
最終日、いい形で締めくくれるように
みんなと楽しく終われるように
今日も楽しむ🕊
ネガティブな意見
5ヶ月間新人研修って長すぎだと思うんだけど民間だとこんなもんなのかなあ
— rkk(りかこ) (@5c9291) April 12, 2021
新入社員研修の目的
ちなみに、会社としては以下のような目的で研修を組み立てています。こうした目的を理解していると、長い期間の研修にも意味を見出せるかもしれません。
1.社会人マインドの醸成
学生気分から脱却し、社会人としての姿勢や考え方を身に付けるための研修。知識教育というよりは、マインド面の研修です。
2.ビジネスマナーの習得
社会人として最低限必要なマナーを学びます。名刺交換や電話・メール対応などの基礎を学びます。
3.基礎的なビジネススキルの習得
報連相やITスキルなどの基本的なスキルを学びます。実務に携わらないとわからないことも多いため、基礎の基礎を学ぶ研修です。
4.専門知識・スキルの習得
技術職や専門職の場合、配属後の業務に必要な専門スキルを学びます。専門性の高い職種の場合、この期間が数ヶ月に及ぶケースもあります。
5.自社の理解
各会社には固有の文化や歴史があります。ミッション・ビジョン・バリューや社内用語、社内ルール、問題解決手法などを知ることで、組織にどれだけ早く馴染めるかが変わってきます。
2)現場実習に送り込まれる
2つ目は「現場実習に送り込まれる」です。
特にメーカーに就職した方の多くは、この現場実習を経験することになります。
Twitterでは以下のような意見がありました。
ポジティブな意見
メーカーに入社した院卒や博士卒を数ヶ月工場実習させるの否定的な意見見る時あるけど、現場を知らない奴に良い製品や技術は開発出来ないよ。現場を知って知見を広めな若者よ
— ラッシュ (@RUSH_poke_trade) September 8, 2019
ネガティブな意見
工場実習、教える側も大変だって聞いたことあるな。「将来的に工場で働かない人にわざわざ時間手間かけて教える意味がわからん」って言ってました。危険な作業はさせられないし。
— 歯車のYoshida⚙️ (@Gear_Yoshi) April 29, 2022
ビデオ研修やwebinarで知識をインプットして、あとは工場見学&交流会でいいのでは?と僕も思う。
現場実習の目的
現場実習の目的は以下の2点です。
① 製品を作る/売ることの実態を知る
② 現場との向き合い方を知る
主にオフィスで働くホワイトカラーの社員が普段は感じることのできない「現場」を体験し「製品を作る/売ることの実態を知る」こと、また、それに従事する現場の方々との向き合い方を知ることが現場実習の目的です。
個人的には、ホワイトカラーも現場を知らないといい仕事はできないと思いますので、現場実習は非常にいい機会だと感じていました。
現場実習の目的についての詳細は以下の過去記事で解説しているので、是非こちらも併せてご覧ください。
3)配属ガチャ・上司ガチャでハズレを引く
3つ目はいわゆる「配属ガチャ・上司ガチャ」です。
一般的な日本の大企業では入社後の職種を限定しない「総合職」として学生を採用し、配属先は入社後に決定します。
入社後に配属希望を出すことはできますが、ある部署を希望する人数が必要人数を超えた場合、超えた人数分は希望以外の部署に配属されます。
この「配属ガチャ」は新入社員のあるあるであることに加え、中堅以降に希望していない異動や出向を命じられる可能性は十分あり、会社人生にずっとついてまわる”あるある”だとも言えます。
また、「上司」についても自分で選ぶことはできません。
どんなに良い会社でも、上司・先輩との関係は所詮「人と人の関係」。どうしても合わない人は当然いますし、中にはハラスメントに近いような人や、マネジメント能力が全くないような人がいるのも事実です。
Twitterでは以下のようなコメントがありました。
ポジティブな意見
配属ガチャは希望する職種につけないデメリットはあるが、本人が思いもよらなかった才能が見つかる可能性もある。
— 黒羊@何かを生産管理する人 (@jewelblacksheep) February 6, 2023
生管•生技•保全等々を最初から最適と考える学生はいないであろう。
災い転じて福となすかは本人の仕事への心がけ次第である。
ネガティブな意見
同期入社の皆様にお前のチームはフロアで一番ヤバそうと言われているので配属ガチャで外れを引いたようです
— Q長@減量バトル中 (@q_cho) December 13, 2019
どんなに優良な大企業・ホワイト企業でも「上司ガチャ」や「配属ガチャ」は存在します。個人的には、ガチャを当てようとするよりも、「外れた時にいつでも環境を変えられる力をつける」努力をするのが大切かもな、と思ったりします。
4)飲み会幹事を若手がやらされる
4つ目は「飲み会幹事を若手がやらされる」です。
特に体育会的な上下関係が残っている大企業では、新入社員や若手が飲み会幹事をやらされることが多くあります。
Twitterでは以下のようなコメントがありました。
ポジティブな意見
今思うと新人に飲み会の幹事やらせるの、メチャクチャ貴重な研修やんな。あれで学べる事すげぇ有るぞ
— おしやびーた (@bitaoshiyan) February 1, 2023
ネガティブな意見
飲み会の幹事や司会やらされるとホントめんどい。新人なら当たり前?
— くろ (@8cpSrZFOh7K0kro) January 8, 2023
そうですか…
飲み会幹事をやらされる理由
部下の育成をしっかり考えている上司の場合、新入社員に飲み会幹事を任せるのには「人材育成上の意図」があります。
しかし、幹事を任された新入社員からすると「バリバリ働こうと思ってたのに飲み会幹事の仕事かよ!」と思ってしまうのも無理はないと思います。
飲み会幹事を任せる人材育成上の意図については、以下記事で詳しく解説していますので、是非併せてご覧ください。
5)ぶら下がりの働かないおじさんが多い
5つ目は「働かないおじさんが多い」です。
「妖精さん」とも呼ばれる働かないおじさんですが、終身雇用・年功序列の文化が根強い日本では、どんな大企業にもかなりの数が存在します。
Twitterでも多くのコメントがありました。
働かないおじさんに関するコメント
40代の部下とはなしていると働かないおじさんではなく、働けないおじさんということがわかってきた。
— さとる (@tenshokutogori) February 9, 2023
仕事をどう進めて良いかわからないので思考停止しているケースが多い。
1〜99まで言わないと仕事ができないのは辛い…
めったに解雇をしないJTCではどこも、働かないおじさんが多い(でも地頭は良い)のってきっとこれが原因ですよね。
— みのるん☁️ (@minorun365) February 5, 2023
個人に悪気があるわけではなく仕組み上、社会心理的にしょうがない現象。
僕らもこうなり得るんですよ… https://t.co/N7gN86ZVmB
働かないおじさんが生まれる理由
働かないおじさんがなぜ生まれるのか、そして自分がそうならないためにどうすれば良いのかは以下の記事で詳しく解説していますので、是非併せてご覧ください。
6)報連相ができず上司から怒られる
6つ目は「報連相ができず上司に怒られる」です。
仕事の基本である報連相ですが、新入社員の頃は難しく感じるもの。私も報告や相談のタイミングが掴めず上司に怒られていた記憶があります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
報連相に関するコメント
報連相って難しいね、他の人を混乱させちゃうし、迷惑になる。(←当たり前)
— GENIUS ていふぁ💭 (@teyfaxd) September 27, 2022
最初は失敗しても修正すればいいけど何度も同じミスをするのはダメだ。
新人若手に「まずは報連相!社会人の基本!」とか言うけど、先輩上司はできてるの?言いっぱなし、聞きっぱなし、怒ると過去まで遡って否定する、FBしないって…そんなだからこっちは信頼できないんだよ。報連相する気にもならないんだよ。って思ってた時代のことを忘れずに生きていきたいと思います。
— えなりんご@フリーランス広報PR (@erinapple_pr) April 2, 2022
報連相の基本
苦手に感じる人の多い報連相について、基本とコツを以下の記事で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
7)仕事がぬるい・楽すぎる・ぬるま湯
7つ目は「仕事がぬるい・楽すぎる・ぬるま湯」です。
これは全ての会社に共通するわけではありませんが、大企業は人員が豊富であったりオペレーションが確立していることから、特に新人の頃は仕事が楽な場合があります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
大企業のゆるさに関するコメント
驚きです。なんと職場が「ホワイト過ぎて」やめる若手が増えています。リクルートワークス研究所の調査で、大企業につとめる3年目以下の49%が「ほかの企業や部署で活躍できない不安」があり、職場を「ゆるい」と感じた人の16%が「すぐに退職したい」と回答。若手が会社にガッカリしてしまう理由は、「
— しゅん (@sunsuke2) December 18, 2022
8)成長できない・スキルが身につかない
8つ目は「成長できない・スキルが身につかない」です。
大企業では新人のうちはエントリージョブとして定型業務を任されることが多くあります。そのため、最初から責任ある仕事を任されるベンチャー企業と比べて、「成長が遅い」と感じる人もいます。
ちなみに、個人的には、仕事の型を身につけるために大企業のような形式は悪くないと感じています。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
大企業の成長スピードに関するコメント
大企業とベンチャーで働いて分かったけど”個の成長”を強く求められるのは圧倒的に後者。成長スピード、期待を越える成果、それを成すための量。求められるレベルが高いほど成長は加速する。キャリアをつくる上で一度はベンチャーも経験しておくと、高い成果をあげる意識が磨かれるのでオススメです。
— ななと (@nanato_noto) February 14, 2022
大企業は成長できないは間違い
個人的には、大企業はスキルがつかない・成長できないというのは間違いだと思っています。大企業だからこそ身につけることができるスキルについて以下の記事で解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
9)業務が調整ばかりでつまらない
9つ目は「業務が調整ばかりでつまらない」です。
大企業では部署が多くあり、レポートライン(上司や上司の上司)も多くいることから、社内の調整に多大な工数がかかります。若手の頃はこの調整だけで多くの時間を使うことが多々あり、仕事がつまらないと感じる一因になっています。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
調整業務に関するコメント
先程お客様から稟議が通ったとお電話を頂く。大きい組織であればあるほど、社内調整が大変。銀行員の時も社内の稟議を通すのが一番大変だった。大企業で活躍するには社内調整力が最も大事な気がする。
— イッシー/転職コンサル・採用マーケ支援 (@issyjinsei100) November 8, 2022
この仕事クソだな、と思うことがありますが、考えてみると全部大企業ならではの調整業務。
— めんへら|貯蓄0からのFIRE (@menhealerorz) February 6, 2023
大したバリューも生み出してないのに、平均より高水準の給料がもらえてるのは、大企業だからか、と自分を納得させながら働いてます。
10)組織が縦割りで交流がない
10個目は「組織が縦割りで交流がない」です。
大企業では数千人から数万人の従業員が在籍しているため、「本部」や「部」といった名称の組織が大量にあります。そしてそれぞれの組織に数百人の従業員が所属し、分業体制が引かれています。
そのため、特に若手の内は所属部署内でしか仕事をせず、他部署と関わる機会が少なくなります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
縦割りに関するコメント
小さい会社で全体を見通していると、マーケも営業も採用も人事も教育も広報も経理も、すべてが相互依存しあって成り立っていることを実感します。どこかの紐を引っ張ると全体が引っ張られる感じ。大企業のように縦割りで組織を作ると解決が難しい問題を抱えがちなのもよく分かります。
— sogitani / baigie inc. (@sogitani_baigie) July 1, 2019
大企業に行けば大きい仕事ができると思ってる方がいますが、半分正解、半分不正解。
— きょん@ 最強にロックなオカン (@kkkyonhpl) February 23, 2020
昔、建築業界の最大手にいたけど、限られた範囲の仕事しかできなかったし、10年20年上の先輩も同じ事してた。社内分業が徹底されてたら当たり前のこと。私はベンチャーで、自分の得意分野、好きな事に気付けた。
11)ルールがガチガチ
11個目は「ルールがガチガチ」です。
大企業には数千人から数万人の本当に様々な従業員がいます。そのため、かなり細かいことまでルールが決められており、一見すると「無駄なルール」や「管理のための管理」のように見えてしまうことがあります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
大企業のルールに関するコメント
大企業って、統率取るためにガチガチのルールって必要だと思うけど、
— ニナ沢 (@nina_serizawa) March 10, 2019
例外も作れないのは、どうかと思った🤔🤔🤔
例外つくると、もっと伸びる方向もあるのになあ。
せっかく社員のため、と思って作ったルールや福利厚生でもそれを悪用する人がいれば、やっぱりその制度はやめよう、となってしまう。そうして性悪説にたつことによってガチガチになった日本の大企業は多いんじゃないだろうか。
— もふもふライオン (@mofumofu_LION) January 12, 2021
12)社内向けの無駄な仕事が多い
12個目は「社内向けの無駄な仕事が多い」です。
コロナ禍によってだいぶ変わった印象もありますが、かつての大企業では「紙資料」「はんこ」「発言内容の決まった会議」「役員会議のリハーサル」といった無駄な仕事が多く存在しました。
長く大企業にいると「それが仕事だ」と思うようになってしますのですが、客観的に見ると「無駄」と言える仕事がまだまだあると思います。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
社内向けの仕事に関するコメント
先日友人が言っていた「本当に優秀な人は大企業にはいない。みんな辞めてスタートアップ行くか起業してる」という言葉が印象的でした。
— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) June 16, 2021
大企業は社内向けの仕事が多く、歳取って役職が上がれば上がるほどビジネスより政治に使う時間が増えるから、「優秀な政治家」か「ぶら下がり社員」しか残らない。
大企業は社内向けの非生産的な仕事がとても多いね。なので、忍耐強くないとやっていけないし、空気も読まないといけないから、上に登り詰める人は非常につまらなかったりする。
— 品川 要 (@kanameshinagawa) August 3, 2020
やはり、それなりに稼ぎきったところでスパッと辞めて、自営業やるのが一番楽しいんじゃないかなぁ。
13)提案やチャレンジをしにくい
13個目は「提案やチャレンジをしにくい」です。
特に若手のうちは、新しい提案やチャレンジングな提案をしても、上司や先輩から否定ばかりされることがあります。
「新人の目から見ておかしいと思うことはどんどん提言してほしい」という歓迎の言葉は嘘だったのか、と思ってしまうこともあると思います。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
提案やチャレンジに関するコメント
前職の大企業在籍中に、トップの方針であるチェンジ&挑戦を踏まえて、新ビジネスをどんどん提案したが、各部門の中間管理職らにことごとく否定され実現出来なかった。今、独立して、それらを形にすることで、お陰様で予想以上の実績をあげている。大企業はこうやって潰れていくのだ。もったいなー。
— T.sky (@Tsky28051552) January 25, 2022
大企業はいいと思うぜ。給料ももらえるし、おもしろい仕事もある。
— 松永宇祥(たかよし) (@MatsunagaTaka) May 13, 2020
けど大企業の居心地の好さに慣れてしまうと、ゆでガエルになるから注意だ。
若手の提案を、できない理由を並べて否定する。だけど、それに対案を言うわけではなく、現状を何も変えられない人。。
そんな人に…なりたくはないぜ。
14)稟議や決裁に1週間以上かかる
14個目は「稟議や決裁に1週間以上かかる」です。
大企業では部門・部・室・課といった組織の階層があり、それぞれにマネージャーが配置されています。そして大事な案件であればあるほど、上位のマネージャーの承認が必要になります。
そのため、場合によっては直属の課長決裁→室長決裁→部長決裁→本部長決裁というように、多くの承認を得る必要があります。また、各決裁で質問ややり直しが発生することも多く、一つの稟議を通すのに1週間以上の期間がかかることもザラにあります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
稟議や決裁に関するコメント
大企業に所属していると
— かいとさん|音楽をくりえいとする人 (@s_kaitosan) September 30, 2020
「自分の理想ややりたい事」に対して
稟議を通す時間と労力がかかりすぎる事。
会社である以上、当たり前だけど稟議を通される側の度胸も試されるので
尻拭いしたくない人が上に立つと
ほんとやりたい事できないです。
企業のほとんどがそうだろうね。#大企業#ホワイトカラー
日本のスタートアップが大企業に勝てる、その大いなる強みになるのは、稟議を回さなくすむからフットワークが軽いこと。逆に言えば、組織の拡大につれ承認プロセスが煩雑化するにつれ、その利点は雲散霧消する。
— とみおか_いさお@ストーリーテラーインキュベーター/新規事業開発 (@Isao_Tomi) August 1, 2022
事業開発者にとって、「稟議を通すため」は、思考停止と時間の浪費の大いなる言い訳
15)社内資料の体裁に非常にこだわる
15個目は「社内資料の体裁に非常にこだわる」です。
大企業にいると決裁資料や報告資料など、多くの資料を作成します。これらの資料の多くは社内でのみ使用されるのですが、その体裁に非常にこだわります。
誤字脱字程度ならわかるのですが、「左右の余白の幅」や「フォントの種類・大きさ」など、非常に細かい点まで上司から指摘されることがあります。資料の見た目が美しいのはいいことですが、やりすぎでは・・・と感じることも多々あります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
資料の体裁に関するコメント
大企業は有名大学の人を採用する
— 社労士を目指すゴマ (@sharoushi_goma) April 29, 2021
だけど就職して最初に求められるのは
・正確な事務作業
・体裁の良い資料作成
・上司への話し方 です
これが出来ないとクリエイティブな業務は与えられないし、昇格出来ない
残酷ですが勉強出来ても
上の能力が無いと大企業では詰みます
これマジです
大企業とベンチャーどちらも経験してわかったこと。
— 濱田 将伍 | Webマーケティング (@shogo_08) March 12, 2022
・大企業は資料の綺麗さ・洗練さが大事
・ベンチャーは資料の体裁よりも内容・結果が大事
どっちも経験することで対応の幅が広がるし、クライアントに合わせて満足度を上げられる。
16)周りが優秀でついていけない
16個目は「周りが優秀でついていけない」です。
就職人気の高い大企業には有名大学の出身者など優秀な人がたくさんいます。
新入社員研修でも地頭の良さや発言のロジカルさなどに周りとの差を感じてしまうことがあると思います。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
周囲が優秀であることに関するコメント
大企業も良い事業してるし、有能な人も多い。
— まらりん@ヘビー級お荷物社員 (@mararin_bottom) March 8, 2021
僕は大企業(の孫会社)にいるけど、周りが優秀すぎて全然ついていけない。
中途入社の人も、けっこう多い。
「大企業無能説」は、自分にとっては嘘でした。
情報系の院卒も大量にいるので、使えない人だらけだとは思わない……
— まらりん@ヘビー級お荷物社員 (@mararin_bottom) April 17, 2021
研究職とかもあるし。
自分は大企業の孫会社に勤務しているが、周りも親会社も研究所の人も優秀すぎて、まったくついていけない……
17)副業が禁止されている(という勘違い)
17個目は「副業が禁止されている」です。
副業人気が高まる中、大企業の中には副業を解禁していない会社が多くあると言われています。
実際、就業規則には「会社の許可を得ずに副業をすることは禁止する」と記載されていることが多く、「うちの会社は副業禁止だよ」と先輩や上司から言われることが多くあります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
大企業の副業に関するコメント
【大企業あるある】
— 納豆@モヤモヤ若手の悩み相談 (@Nattou_lucky777) September 20, 2022
副業禁止
副業禁止の企業は、未だに多いです😵
法律上はOK、でも社則でNG、という構図🤔
調査結果を見ても、なーんか自社に都合が悪いから禁止って感じですね💦
個人的には、副業禁止するなら将来の収入保証すべき、と思ってますが、
それができる日本企業があるのかどうか…😔 pic.twitter.com/XoccaPPqv2
「本業に支障が出るから副業禁止!」とか言っちゃう大企業は、それなら毎週強制の飲み会もゴルフ接待も全部やめろよな!本業に支障出るからさ!
— あんちゃ/執筆屋 (@annin_book) February 18, 2018
実は勘違いであることも多い
しかし、実は副業禁止というのは勘違いであることも多くあります。
冒頭の「会社の許可を得ずに副業をすることは禁止する」という文言は、裏を返せば「会社の許可を得れば副業ができる」ということでもあります。
直接人事部に確認をしてみると、「積極的に推進していないだけで申請すれば副業可能」というケースも多々ありますので、一度人事部に確認してみることをオススメします。
18)優秀な人が辞める
18個目は「優秀な人が辞める」です。
最近は転職が当たり前になっていますが、それは大企業も例外ではありません。会社の中で優秀者と見られていた人が転職をしてしまうことも多くなっています。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
優秀者の退職に関するコメント
大企業では、退職勧告で優秀な人から辞める。能力のない人は辞めない。
— NA税理士法人 NA社会保険労務士法人 (@na_tax_t) December 18, 2020
中期業では、能力のない人が肩たたきされる。
中小企業では、成長しない会社の社員は辞めない。成長している会社は能力のない社員が辞める。
心地悪くなる。能力のある社員が成長してゆく。
小山昇氏の言葉#経営者の言葉 pic.twitter.com/vNqx3ItdcQ
早期退職制度なんて優秀な人材ほど古臭い大企業を見限って出ていくに決まってるんだから愚かしい制度なんだけど、なぜそれをやるか。解雇規制が厳しすぎるからでしょう。 https://t.co/bSKM2ItBvf
— CoffeeCup (@coffeecup2018) October 2, 2021
19)若手の退職が多い
19個目は「若手の退職が多い」です。
転職の波は特に若手に強く押し寄せています。
入社3年目までに転職をする人が大卒でも3割を超えると言われていますが、それは大企業も例外ではありません。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
若手社員の退職に関するコメント
ここ2年間の大企業の新入社員の退職理由がきわめて健全。「チャレンジできない」「このスピード感ではは自分が時代に取り残されそうで怖い」
— 沢渡あまね新刊 #話が進む仕切り方 #越境思考 等 #組織変革Lab 主宰 (@amane_sawatari) December 27, 2017
経営者の皆様にやっていただきたいこと2つ。若手がチャレンジする場を創って!無駄な間接業務をとにかくなくして!
国立大学の教員と話していたら、大企業や国家公務員になった優秀な学生が3年以内に退職する例が増えていて、問題になっているそうです。理由は、30代や40代の先輩を見て絶望するから。「あんな人生はぜったいにイヤだ」というそうです。ここに日本の病巣が集約されていますね。
— 橘 玲 (@ak_tch) February 24, 2016
20)うつ病で休職する人が多い
20個目は「うつ病で休職する人が多い」です。
大企業では各部署に休職(数ヶ月単位の休務)をしている人がいることが多くあります。病気や怪我の場合もありますが、多くのケースで適応障害やうつ症状でお休みをされています。
大企業とはいえ、様々なプレッシャーの中で仕事をしていると、どうしてもメンタルヘルスに不調を来してしまう人が一定数いるのです。実際、就業規則には「会社の許可を得ずに副業をすることは禁止する」と記載されていることが多く、「うちの会社は副業禁止だよ」と先輩や上司から言われることが多くあります。
Twitterにも以下のようなコメントがありました。
メンタルでの休職に関するコメント
昔ね、大手の証券会社で働いてたし旦那が今大手大企業で働いてメンタル壊して休職中なので大手企業の闇はそれなりに存じ上げております。私は適度な中小企業方が性格的に合ってました。
— こっこ🗝 (@Cocco_secret) November 21, 2022
大企業でメンタルをやられた3つの要因↓
— しんいち@スラッシュキャリア (@webwriter_shin) April 19, 2021
1⃣「オレの言う通りにしとけ」「はい!」という上下関係
2⃣社歴が長い”お局さん”達へのご機嫌伺い
3⃣新しいことを1提案すると10の批判が帰ってくる
離職率が低いぶん、大企業の職場は「ムラ社会」。ムラの掟を守れないと、自主退職か休職かを選ばされます😣
2.モヤモヤ・不安の解決策
1)自分の市場価値を確認する
将来的に転職を決断した場合、どれぐらいの年収を狙うことができるのかを知るために、定期的に自分の市場価値を診断しておくことは非常にオススメです。
無料で市場価値診断をする場合、非常にオススメなのが「VIEW」という無料アプリです。
「VIEW」はAIが分析してくれるキャリア+市場価値診断として人気が急上昇中のサービスで、経歴や価値観に応じた10以上のキャリアシナリオとそれぞれの想定年収を提案してくれます。
詳しくは以下の記事で解説していますので、是非併せてご覧ください。
2)自己投資・スキルアップをする
社内異動で「良い環境」を探したり、「良い上司」に巡り会うのを待つことも手段ではありますが、個人的には、「環境が悪くなったときにいつでも環境を変えられる力をつける」努力をするのが大切だと思います。
そのために、会社の仕事だけでなく、自己投資・スキルアップの努力をするべきです。
大企業社員にオススメの自己投資・スキルアップは以下の通りです。
① 読書
② オンライン学習サービス
③ 副業
読書については、本を読む時間がなかなか取れない場合、本の要約サービスflierフライヤーを活用するのがオススメです。ビジネス書をはじめ、2700冊以上の厳選された本の要約を読むことができます。
早速市場価値診断をしたい場合は、以下リンクからアプリをダウンロードしてください。
3)上司に異動を願い出る
大企業の場合、社内には多くの本部や部があります。また、年に1・2度はキャリア面談の機会があり、異動希望を提出することができようになっています。
もし、今感じているモヤモヤや不安が、社内の異動で解決できる可能性があるのであれば、まずは異動希望を上司に提出してみるのがオススメです。
4)専門家にキャリア相談する
転職をするかどうかに関わらず、専門家にキャリアについて相談し、客観的なアドバイスをもらうこともオススメです。
有料サービスはハードルが高い場合、無料でキャリア相談をするには転職エージェントのキャリアコンサルタントに相談するのがオススメです。
20歳代の若手の方の場合、第二新卒や若手の転職に定評のある「マイナビエージェント」に相談をするのがオススメです。
マイナビエージェントについて、詳しくは以下の記事で解説しているので是非ご覧ください。
早速マイナビAGENTに相談したい場合には、こちらから公式サイトHPをご覧ください。
5)転職活動を始めてみる
転職するにしてもしないにしても、新入社員として会社に入社した時から転職活動をしてみることは、キャリアを考える上でおすすめです。
私自身、入社1年目から転職エージェントに登録していましたが、「自分の経験値だとどんな求人があるのか」を知れたり、「無料のキャリア相談で頭の中が整理」されたり、非常に有益でした。私は結果的にそれが転職につながりましたが、「もしいい求人がいいタイミングであれば転職も考える可能性がある」ぐらいの気持ちで全く問題ありません。
個人的にお勧めするのは以下の転職エージェントです。
若手の転職におすすめの転職エージェント
① 20代の転職に強い「マイナビエージェント」
② 20代のための就職・転職支援【えーかおキャリア】 ![]()
3.まとめ
この記事では、大企業勤務の若手が感じるモヤモヤや不安の概要と、その解決策について丁寧に解説しました。大企業入社後に若手社員がよく感じるモヤモヤ・不安は以下の通りです。
1)新入社員研修が長い
2)工場実習・現場実習に送り込まれる
3)配属ガチャ・上司ガチャでハズレを引く
4)飲み会幹事を若手がやらされる
5)ぶら下がりの働かないおじさんが多い
6)報連相ができず上司から怒られる
7)仕事がぬるい・楽すぎる・ぬるま湯
8)成長できない・スキルが身につかない
9)業務が調整ばかりでつまらない
10)組織が縦割りで交流がない
11)ルールがガチガチ
12)社内向けの無駄な仕事が多い
13)提案やチャレンジをしにくい
14)稟議や決裁に1週間以上かかる
15)社内資料の体裁に非常にこだわる
16)周りが優秀でついていけない
17)副業が禁止されている(という勘違い)
18)優秀な人が辞める
19)若手の退職が多い
20)うつ病で休職する人が多い
続いて、そんなモヤモヤ・不安を感じた時の解決策は以下の通りです。
1)自分の市場価値を確認する
2)自己投資・スキルアップをする
3)上司に異動を願い出る
4)専門家にキャリア相談する
5)転職活動を始めてみる
解決策に挙げた手段を活用して、自分なりに納得のいくキャリアを切り拓きましょう!
4.関連記事
1)大企業で働くメリットデメリットについて
以下の記事では、大企業に金んむするメリット・デメリットを10ずつまとめています。
2)仕事と育児の両立について
以下の記事では、大企業で仕事と育児を両立する参考に、実際の子育て支援や女性活躍の取り組みをまとめています。

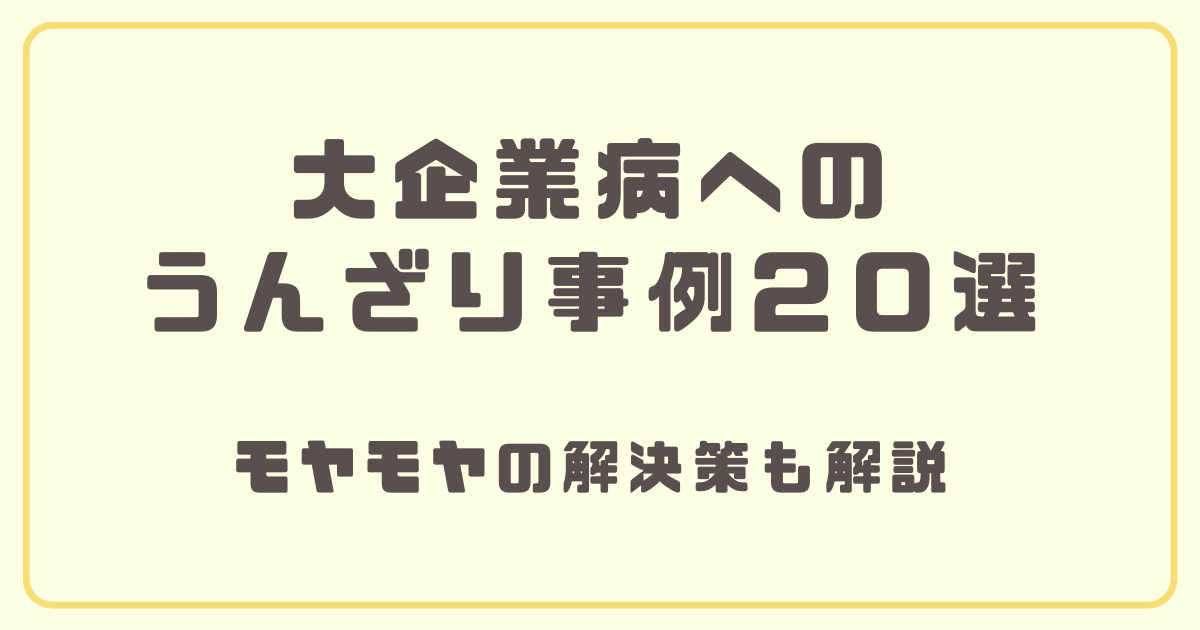

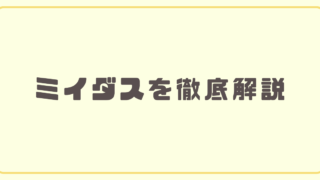






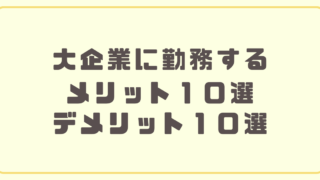


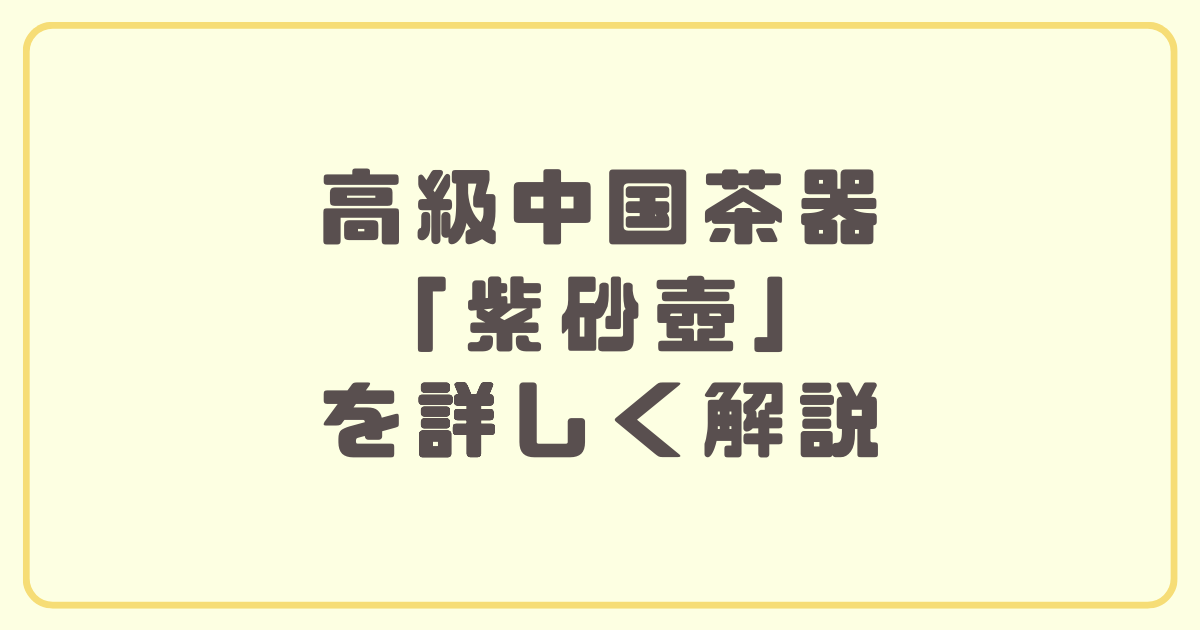
コメント